「石を拾うのが趣味なんです。」と、相手に伝えて何度拍子抜けした顔を眺めてきたことか。
26歳がもうすぐ終わりを迎える頃、わたしには新たな趣味ができた。厳密にいうと新たにできた、というよりも幼い頃からの習慣を趣味として正式に昇格させた、と表したほうが正しい気もするが。
今回は、”年齢を重ねてひとりで完結ができる、心が踊るような趣味ができることの尊さ”を綴ってみたいな、と思う。

6歳の頃からずっと石が好きだった。
公園で石を拾ったり、連れて行ってもらったりした博物館や出先で石ばかり(旅行先などでよく見かけるあの”色とりどりのおもちゃのような石のセット”も含めて)求めていた。
そこらへんの石を拾ってきて親を困らせたことは、もはや数え切れないくらい。実家の小さな庭は、わたしの拾ってきた渾身の石ころたちばかり。
10代を過ごすにあたって、部活や勉強(一応勉強も入れておく、一応ね。)に打ち込む日々で、次第に石に触れる機会は減ったのだけど、上京後の新居にお気に入りの石を飾ったり、石の展示に足を運んだり、なんだかんだで石との接点は持ち続けていた。
そんなある日、26歳のよく晴れた春の日に小田原の海へ行ったときのこと。

どこまでも広がる海原よりも、わたしが興味を示したのは『石』だった。
夢中になって地面と睨めっこ。じいっと見つめないと、”良い石”を見逃してしまう。それらを見逃さないように、必然的な出会いを見送ってしまわないように、目を凝らす。
帰る頃には両手に石で溢れていた。
たのしくて、うっとりするような時間だった。心の奥底が水を得た魚のように、ぴちぴちと踊っていた。
それから、わたしはあらゆる水辺で石を拾うようになった。(もちろん、持ち帰り禁止の場所や神聖な土地などは例外だ。)
川も海も、その土地ごとに石の形や種類が違うので、面白い。
例えば三津浜の海。水生生物が多いのか、貝殻が多め。小ぶりで、色のある石が多い。浜に流れ着いた砥部焼の破片も。

水色と赤のコントラストが美しい、元レンガの代表のような石や、つるっとした表面が魅力的な粘土色の石たちもいた。変わり種ってやつ。
一方、佐田岬の海の石は、色とりどりで色彩が豊かだ。全体的に海の色を模したような緑がかった石がメジャーなようで、荒波に揉まれたからか丸っこくて平らな石も多い。水切りに向いてそう。
赤黒い石は、火山のような逞しさを感じる。

白い楕円の石は、凛とした佇まいである。
久万高原の山奥の川の石は、大ぶりなものから小ぶりなものまでさまざま。白石系や透き通ったもの、川の流れのような筋が入ったものまで幅が広かった。
特にお気に入りはこれ。朱色、薄い黄色、パープルの石たち。豊富なカラーバリエーションはまるでアイドルのよう。

勾玉のような、くねっと曲がった薄いかたちも愛らしかった。自然の力でどうしてこんなにも湾曲しようものか。

これは、満月のような白くて透いた石。白の斑点がしんしんと降り注ぐ雪のようにも見える。

こんなふうに、1つ1つの石の特徴を捉えて見つめていくのが面白い。
詰まるところ石を選ぶということは、無限にある石の山から、心惹かれる石を選ぶ。選ぶ前までは皆、一様なのに選んだ瞬間から、その石には価値が生まれる。
無数にある選択肢の中から”自分で価値を見出す宝探しのような作業”がワクワクするのかもしれない。

もうひとつ理由がある。
石の形は何十、何百と時を重ねて今、そこにある。その歴史の積み重ねを尊いなとも思うし、たとえ、わたしが死んでしまったたしても、選んだ石たちは残り続ける。ずっと。燃やしたとしても、大抵のことでは崩れない。
その”普遍的”な存在に、いつか終わりを迎える自分の人生の一部を託してみたいのかもしれない。
ということで、「石拾いが趣味です。」と胸を張って言えるようになってから、週末が来るのが待ち遠しい。どんな石に出会えるかな、と思うだけで今まで以上に日常が色付いた。
歳を重ねても気兼ねなく向き合っていける、ひとりで完結できる趣味を持つと、日々の暮らしに精が出て生き生きとするのではなかろうか。
そんなふうに、20代後半を過ごしていきたいし、自分の人生をより豊かになる方向へ、自分の意志と自我で舵をきっていけたらな、と思ったりするのだ。
これがわたしの人生だ、と胸を張って言い続けていけるように。
risa / writer


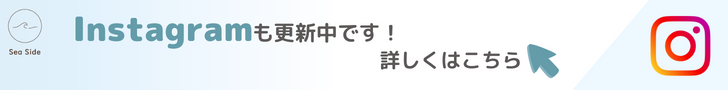

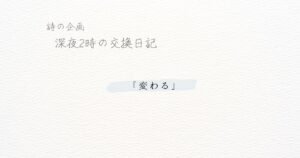


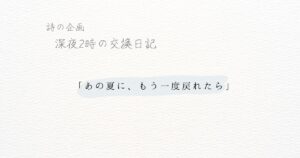




コメント